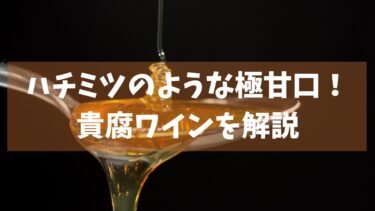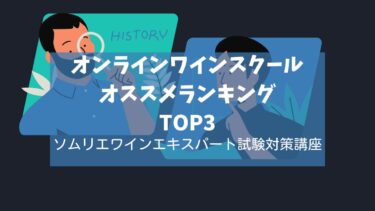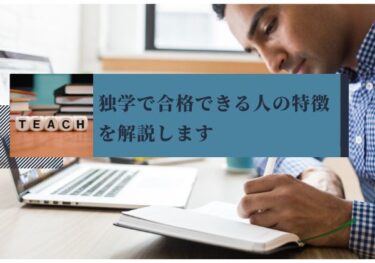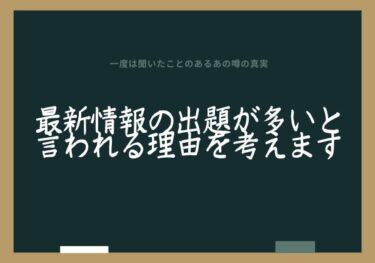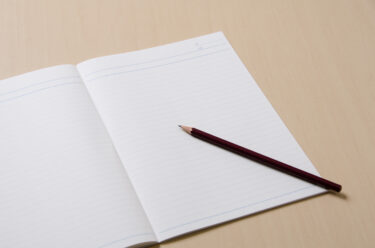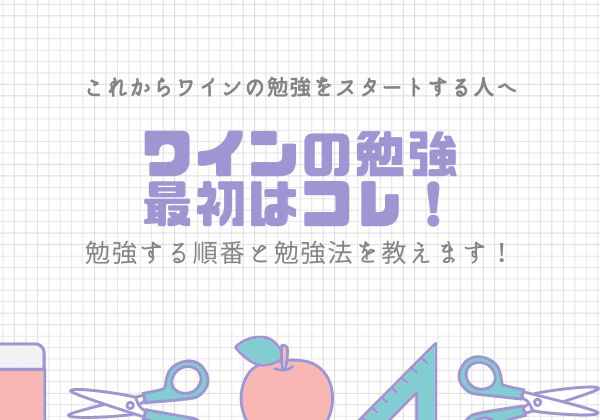- ドイツ語に馴染みがない人が多く苦戦しやすい国
- 13の生産地域と基本情報を押さえる
- 歴史もポイントでチェックしておく
- 旧ワイン法から新ワイン法への転換期のため、新ワイン法は要注意
ソムリエ&ワインエキスパート一次試験対策シリーズ。
今回はドイツです。
ドイツはかつて、ブドウ栽培の北限とも言われていました。
しかし近年は温暖化で気温が上昇し、今ではイギリスについで二番目に北にあるワイン生産国となっています。
リースリングから造る甘口ワインが有名ですが、実は中辛口~辛口が生産量の7割を占めているほか、赤ワインも3割ほど生産されています。
2021年には新ワイン法が制定されました。
2025年頃までは法律の移行期となるため、この新ワイン法に関する出題は多くなる可能性が高いです。
今回はそんなドイツについて重要ポイントをまとめて、最後に練習問題を載せました。
ドイツ語に苦手意識を持つ人が多いですが、出題は基本的なことからがほとんどです。
練習問題を活用して、要点を覚えていきましょう。
全ての記事にランダムで出題される練習問題がついているので試験学習にうってつけ。
独学・スクール通学を問わず、ソムリエ&ワインエキスパート試験合格を目指す人全員に役立てるようになっています。
詳しくは下記リンクの記事をチェックしてくださいね。
ソムリエ・ワインエキスパート試験はワインの難関試験です。 勉強も大変そうだし、何から手をつけたらいいのかもわからないですよね。 筆者は年末頃から少しずつ勉強をスタートして、年明けからはオンラインスクールも利用しながら一発で合格す[…]
ドイツワインの歴史
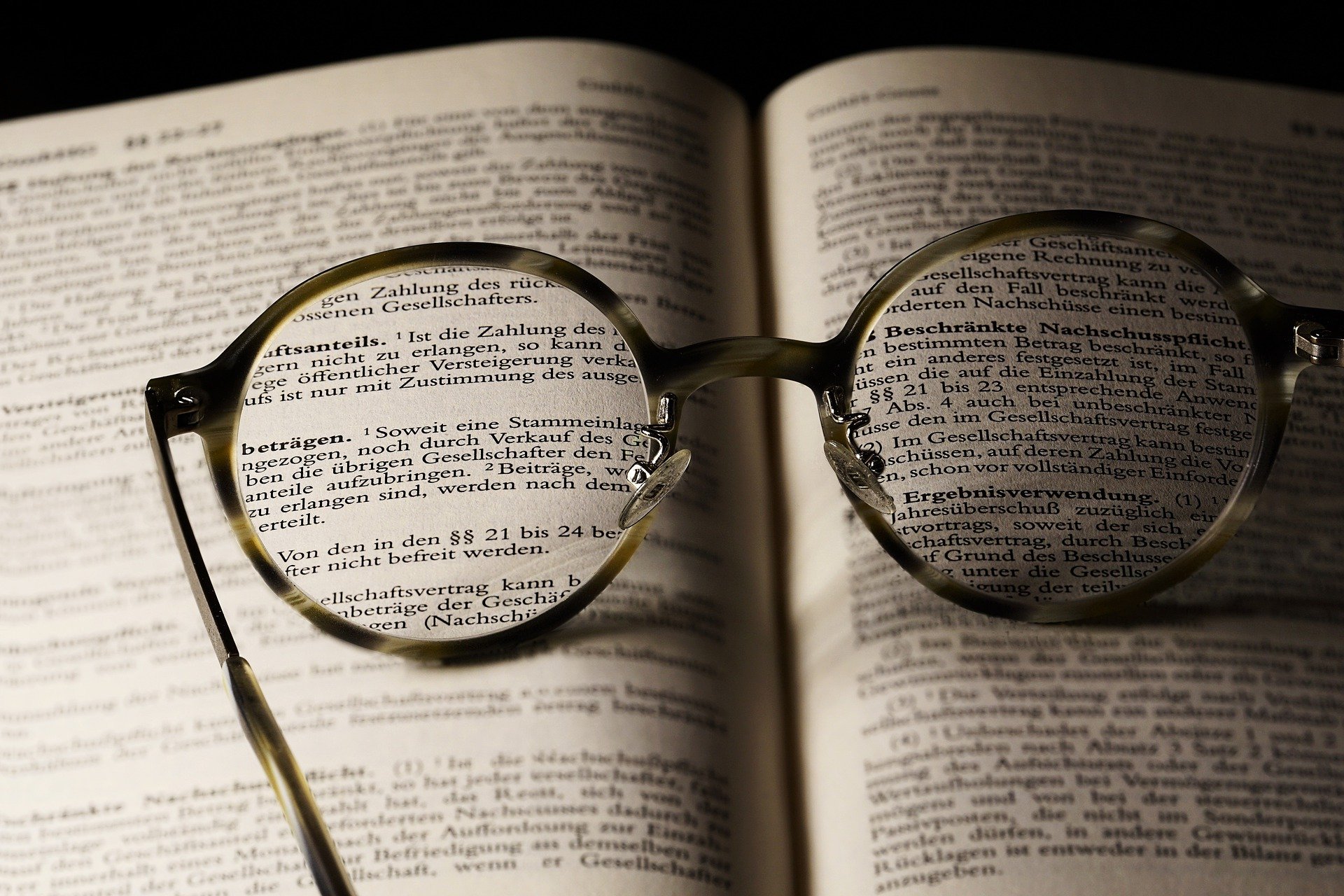
- 12世紀頃からワイン産業が本格化
- 南部では日常品、北部では高級品として扱われた
- 甘口ワインの産地として価値を上げるも20世紀初頭は敗戦などにより輸出向けワインが激減
- 1960~1970年代には景気を取り戻すもジエチレングリコール混入事件により再度下火に
12世紀以降、ドイツ各地に都市が成立すると共にワイン産業は発展していきました。
当時、都市では水の状態が悪く、ブドウ栽培地の多いドイツ南部では水代わりに毎日1~2Lのワインが飲まれていました。
一方ドイツ北部では、地元でブドウの栽培が進まず、ワインは河川の流通を使って運ばれてくるものが主流でした。
そのため日常消費にはビールが好まれ、ワインは高価な嗜好品として扱われることになります。
18世紀頃にはブドウ栽培の改善が行われ、ヨハニスベルクにリースリングが大量に植樹されました。
1775年から、同じくヨハニスベルクで貴腐ワインの醸造が試みられ、1786年にはモーゼルでも低品質なブドウから高品質なブドウの栽培にシフトしていきます。
その後甘口ワインの産地として価値を上げていきますが、第一次世界大戦の敗戦や世界恐慌などにより輸出向けワインは激減。
1960~1970年代の甘口ワインブームで景気を取り戻すものの、オーストリア発端のジエチレングリコール混入事件によりドイツ国内の甘口ワインへの不信感が蔓延し、国内向けには辛口ワインが造られるようになりました。
今回は貴腐ワインについて解説します。 「貴腐ワインって何?」っていう人も多いんじゃないでしょうか。 少しワインを勉強したことがある人なら、「甘いワインってことは知ってるけど…」って人もいるかもしれません。 貴腐ワインの原料[…]
主要品種

- リースリングとピノノワールが最重要
- シノニムや交配の出題も多い
ドイツではリースリングとピノノワールが二大品種です。
シノニムも多く出題されますが、特に
ピノグリ=グラウブルグンダー
は頻出です。
| 主要ブドウ品種 | 備考 |
| Riesling リースリング |
白の栽培面積第1位 白・黒総合でも第1位 |
| Muller-Thurgau ミュラートゥルガウ |
別名:Rivaner リースリング×マドレーヌロイアルの交配品種 |
| Grauburgunder グラウブルグンダー |
別名:Rulander =ピノグリ |
| Spatburgunder シュペートブルグンダー |
黒の栽培面積第1位 =ピノノワール |
| Dornfelder ドルンフェルダー |
|
| Portugieser ポルトギーザー |
ドイツの新ワイン法
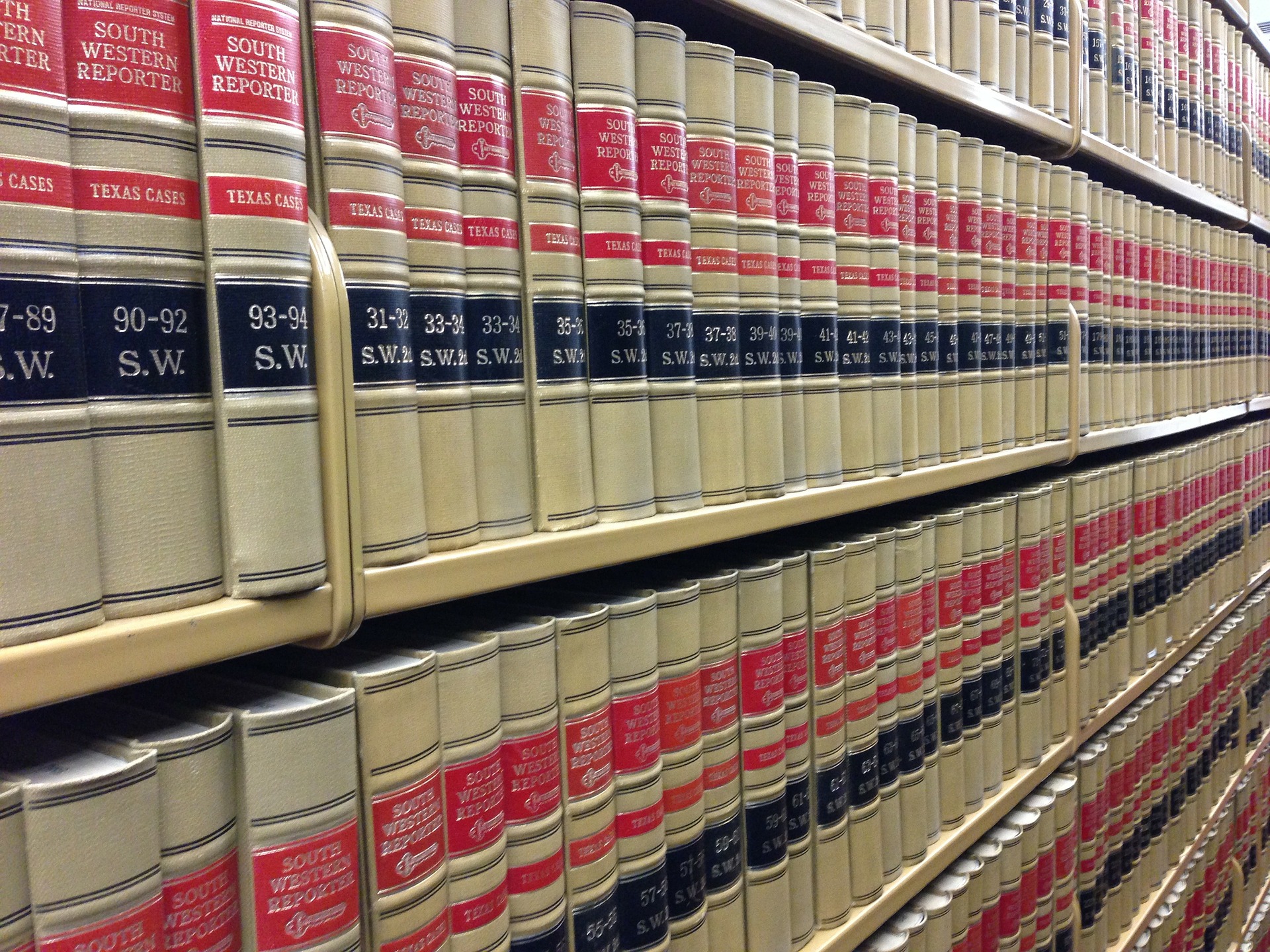
- 2021年1月27日に制定した新ワイン法
- 糖度による格付け評価から地理的呼称による格付けに変更
- 現在は移行期間であり、2025年産までは旧ワイン法の表記も認められている
- 13の特定ワイン生産地域内のみで生産可能
ドイツでは2021年に新ワイン法が制定されました。
これまでは原料ブドウの糖度によって格付けされていましたが、新ワイン法では原産地呼称による格付けに変更されています。
カテゴリー名が非常に長いですが、「g.g.A.」のように略称で覚えればOKですよ。
新ワイン法の地理的表示付きワイン
- Wein mit Geschutzter Geographischer Angabe
- 地理的表示保護ワイン
- EUでいうI.G.P.
- Wein mit Geschutzter Ursprungsbezeichnung
- 原産地呼称保護ワイン
- 旧法律のクヴァリテーツヴァイン
- さらに地域名~単一畑までの4段階に区分けされ、単一畑にはプルミエクリュ、グランクリュも存在する
それぞれの格付けを覚えましょう。
特にグランクリュに相当するグローセス ゲヴェクスは重要です。
| g.U.の格付け | 備考 |
| Anbaugebiet アンバウゲビート |
生産地域名呼称 |
| Region レギオン |
地区名ワイン |
| Gemeinde ゲマインデ |
またはOrtsteil(オルツタイル) 市町村名・区域名ワイン |
| Einzellage アインツェルラーゲ |
単一畑ワイン |
| Erstes Gewachs エアステス ゲヴェクス |
単一畑ワイン プルミエクリュ |
| Großes Gewachs グローセス ゲヴェクス |
単一畑ワイン グランクリュ |
ドイツの旧ワイン法
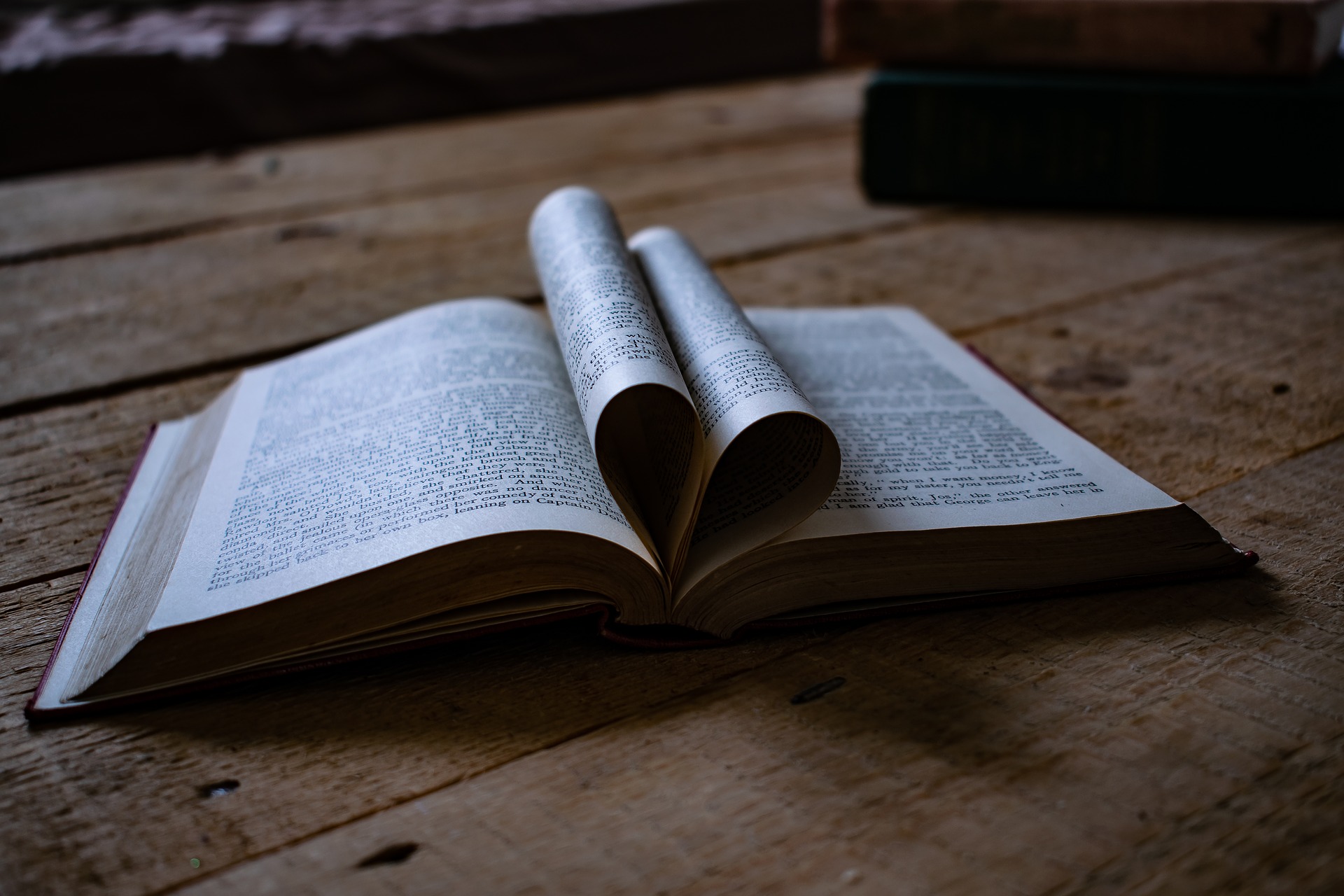
- 2021年のワイン法制定以前のもの
- 2025年産までは旧ワイン法での表記も認められる
- 栽培時のブドウ糖度によって格付けされる
- g.g.A、g.U.は新ワイン法と同じだが、内訳が異なる
新ワイン法が制定されましたが、これまでの旧ワイン法も2025年まで有効です。
原料ブドウの糖度によって格付けが決まるので、こちらも覚えていきましょう。
旧ワイン法の地理的表示付きワイン
- Wein mit Geschutzter Geographischer Angabe
- 地理的表示保護ワイン
- EUでいうI.G.P.
- 26のラントヴァイン(=フランスのVins de Pays)生産地域のブドウを85%以上使用
- Wein mit Geschutzter Ursprungsbezeichnung
- 原産地呼称保護ワイン
- さらにクヴァリテーツヴァインとプレディカーツヴァインに区分けされる
Qualitatswein クヴァリテーツヴァイン
- 13の特定ワイン生産地域のいずれかで造られたブドウを100%使用
- アルコール濃度を補うための補糖が認められる
Pradikatswein プレディカーツヴァイン
- 13の特定ワイン生産地域のいずれかで造られたブドウを100%使用
- 補糖は認められない
- ブドウ果汁糖度およびワインのスタイルにより6つの肩書がある
| Pradikatswein6つの肩書 | 備考 |
| Kabinett カビネット |
糖度:70~85エクスレ以上 |
| Spatlese シュペトレーゼ |
遅摘みブドウで造る 糖度:80~95エクスレ以上 |
| Auslese アウスレーゼ |
完熟or貴腐ブドウで造る 糖度:88~105エクスレ以上 |
| Beerenauslese ベーレンアウスレーゼ |
貴腐or過熟ブドウで造る 糖度:110~128エクスレ以上 |
| Eiswein アイスヴァイン |
氷点下7℃以下で収穫したブドウで造る 糖度:110~128エクスレ以上 |
| Trockenbeerenauslese トロッケンベーレンアウスレーゼ |
乾燥した貴腐ブドウで造る 糖度:150~154エクスレ以上 |
ドイツのワイン法用語

ドイツワインのキーワードです。
いずれも試験に頻出なため、何を意味するのかしっかり覚えましょう。
| ドイツワインのキーワード | 備考 |
| Bestimmtes Anbaugebiet ベシュティムテ アンバウゲビーテ |
13の特定ワイン生産地域の総称 クヴァリテーツヴァイン以上はこの地域のみで生産可能 |
| Bereich ベライヒ |
42地区に分かれる区域 新ワイン法レギオンクラスのワインはベライヒ名を記載する |
| Oechsle エクスレ |
ドイツ人技師 旧ワイン法ではこの測定法で求められたブドウ糖度を○○エクスレ(°Oe)で示す |
ドイツのそのほかのワイン

ドイツを代表するスパークリングワインとロゼワインです。
スパークリングワイン
| スパークリングワイン | 備考 |
| Perlwein ペールヴァイン |
弱発泡性 1~2.5気圧 |
| Schaumwein シャウムヴァイン |
またはSekt(ゼクト) 3気圧以上 瓶内二次発酵のものもある |
| Pet-Nat ペットナット |
ペティヤンナチュレルの略 一次発酵の途中で瓶詰する製法で造る =アンセストラル方式と同じ |
ロゼワイン
| ロゼワイン | 備考 |
| Rosewein ロゼヴァイン |
またはRose(ロゼ) 赤ワイン用品種のみから醸造 明るい色調 |
| Weißherbst ヴァイスヘルプスト |
単一の赤ワイン用品種から醸造 |
| Blanc de Noirs ブラン ド ノワール |
赤ワイン用品種を発酵前に圧搾して造る (一般的な白ワインの製法) |
| Rotling ロートリング |
赤ワイン用品種と白ワイン用品種を混ぜて造る |
VDP. Die Pradikatsweinguter

- プレディカーツヴァイン醸造所連盟という意味
- ドイツのブドウ畑の格付けを推進
- 「VDP.○○」という表記で畑を4段階に格付けしている
プレディカーツヴァイン醸造所連盟が行う格付けも見ておきましょう。
こちらもグランクリュに相当するグローセ ラーゲをまず覚えてください。
| VDP.による格付け | 備考 |
| Gutswein グーツヴァイン |
醸造所名入りワイン |
| Ortswein オルツヴァイン |
地町村名入りワイン |
| Erste Lage エアステ ラーゲ |
プルミエクリュ |
| Große Lage グローセ ラーゲ |
グランクリュ |
13のワイン生産地域

- まずは13地域の名前を言えるようにする
- 特にモーゼルとラインガウが二大産地と言われる
- 最大面積からラインヘッセン・ファルツ・バーデン
- 最小面積からヘシッシェベルクシュトラーセ・ミッテルライン・ザクセン
- 試験対策としては基本的な情報のみをしっかり押さえる
ドイツにはワイン生産地域として認められる13地域があります。
この13地域は暗記して、教本の地図で場所も覚えてください。
それぞれに特徴があるので、おおまかに見ていきましょう。
| 13のワイン産地 | 特徴 |
| Ahr アール |
アール側沿いの産地 旧西ドイツ側の最北端 赤ワインが生産量の80%を超える 主要品種:シュペートブルグンダー |
| Mosel モーゼル |
モーゼル川沿いの産地 ブドウ畑の4割が斜度30度を超える急斜面にある リースリングから造る白が6割 |
| Mittelrhein ミッテルライン |
栽培面積がドイツで2番目に小さい ブドウ畑の85%が斜度30度を超える急斜面にある リースリングから造る白が6割 |
| Rheingau ラインガウ |
ライン川沿いの産地 ベライヒは1つのみ(Johannisberg ヨハニスベルグ) リースリングから造る白が8割 |
| Nahe ナーエ |
ナーエ川沿いの産地 ベライヒは1つのみ(Nahetal ナーエタール) |
| Rheinhessen ラインヘッセン |
ドイツ最大のワイン産地 |
| Pfalz ファルツ |
ドイツで二番目に大きいワイン産地 ドイツで最も温暖な気候 |
| Hessische Bergstraße ヘシッシェ ベルクシュトラーセ |
ドイツで最も小さいワイン産地 ドイツのトスカーナと称される温暖な気候と花崗岩土壌 生産量の90%がオフドライで地元消費 |
| Franken フランケン |
バイエルン州に属する マイン川沿岸の産地 以前から辛口ワインに特化した産地 ボックスボイテル型のボトルにワインを詰める ドイツのシルヴァーナーの起源 |
| Wurttemberg ヴュルテンベルク |
ネッカー川沿岸の産地 ダイムラーやポルシェなどの大企業の本社がある 年間ワイン消費量が47.5L/1人(ドイツの全国平均の倍以上) |
| Baden バーデン |
ドイツで3番目に大きい産地 栽培面積の3割がシュペートブルグンダー 南北400kmの細長い産地で9つのベライヒがある |
| Saale-Unstrut ザーレ ウンストルート |
ドイツ最北のワイン産地 白ワインが7割以上を占める |
| Sachsen ザクセン |
ドイツで最も東に位置する ドイツで3番目に小さいワイン産地 |
Steillage シュタイルラーゲ
- 斜度30度を超える急斜面の畑のこと
- モーゼルやミッテルラインなど
ドイツ練習問題

本記事で解説した内容についてランダムで出題される練習問題を作成しました。
スキマ時間などに是非チャレンジしてください。
最後に
- 新ワイン法の格付けを把握する
- 旧ワイン法は糖度による格付けを把握する
- 13の生産地域の基本情報を紐づける
ドイツはスペルの長い用語が多く大変なイメージですが、出題されるのは基本的なことがほとんどです。
様々なキーワード、ワイン法、産地を中心にしっかり把握するようにしてください。
ソムリエワインエキスパート試験の勉強法はこちら↓
ソムリエ・ワインエキスパート試験はワインの難関試験です。 勉強も大変そうだし、何から手をつけたらいいのかもわからないですよね。 筆者は年末頃から少しずつ勉強をスタートして、年明けからはオンラインスクールも利用しながら一発で合格す[…]
試験に向けてワインスクールを探している人はこちら↓
今回はソムリエワインエキスパート試験対策講座をオンラインで受講できるオススメなワインスクールTOP3をランキング形式で紹介します。 「仕事や家事が忙しくて定期的にスクールに通えない」 「通学圏内にワインスクールがない」 こんな人には自[…]