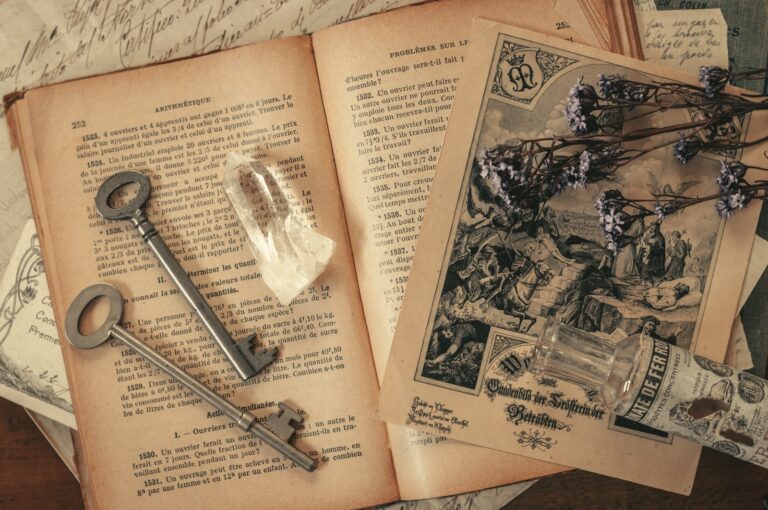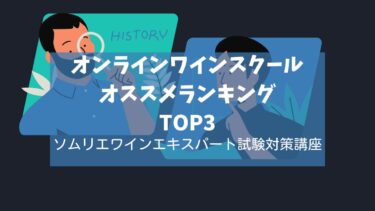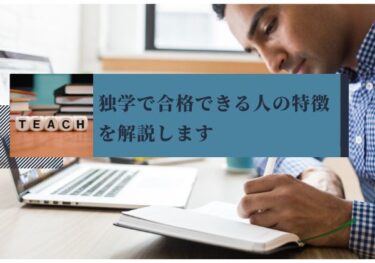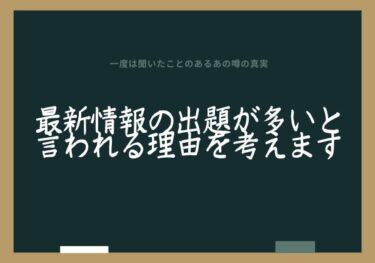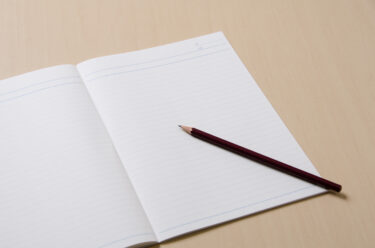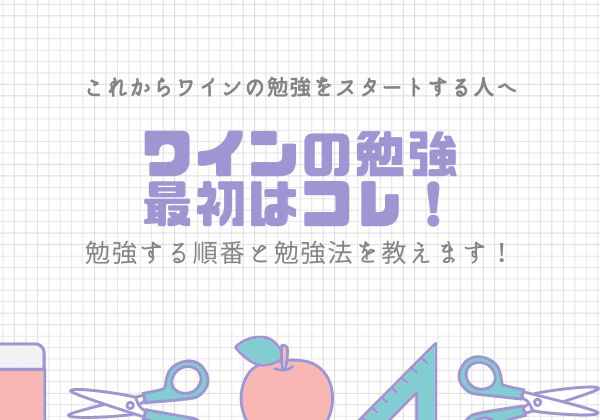- 「ワイン法制定」「最初に〇〇した年」など出題しやすいポイントを把握する
- 日本の歴史は出題されることが多い
- 大まかな時系列も把握しておく
ソムリエ&ワインエキスパート一次試験対策シリーズ。
今回は主要ワイン史の年号です。
ソムリエ&ワインエキスパート試験では、各国のワイン法制定年や、最初にワインが造られた年号なども出題もされます。
Q.フランスでA.O.C.法が制定された年を選べ
1.1933年
2.1934年
3.1935年
4.1936年
一次試験は選択式ではあるものの、例題のように1年ごとの選択肢で出題されると「だいたい1930年代」のような紐づけでは不十分になることも。
この記事では特に問題にしやすい「ワイン法制定年」「最初に○○した年」をピックアップして年表にしました。
日本は近年出題頻度が増加しているので少し多めに抜き出しています。
特に2000年以降の近代史についてはしっかり把握するようにしましょう。
今回のように単純な丸暗記は、軽く頭に入れて練習問題を何度も解くのが暗記の最短ルートです。
最後にランダムで出題される練習問題を載せていますのでご活用ください。
全ての記事にランダムで出題される練習問題がついているので試験学習にうってつけ。
独学・スクール通学を問わず、ソムリエ&ワインエキスパート試験合格を目指す人全員に役立てるようになっています。
詳しくは下記リンクの記事をチェックしてくださいね。
ソムリエ・ワインエキスパート試験はワインの難関試験です。 勉強も大変そうだし、何から手をつけたらいいのかもわからないですよね。 筆者は年末頃から少しずつ勉強をスタートして、年明けからはオンラインスクールも利用しながら一発で合格す[…]
ワイン法制定の年号
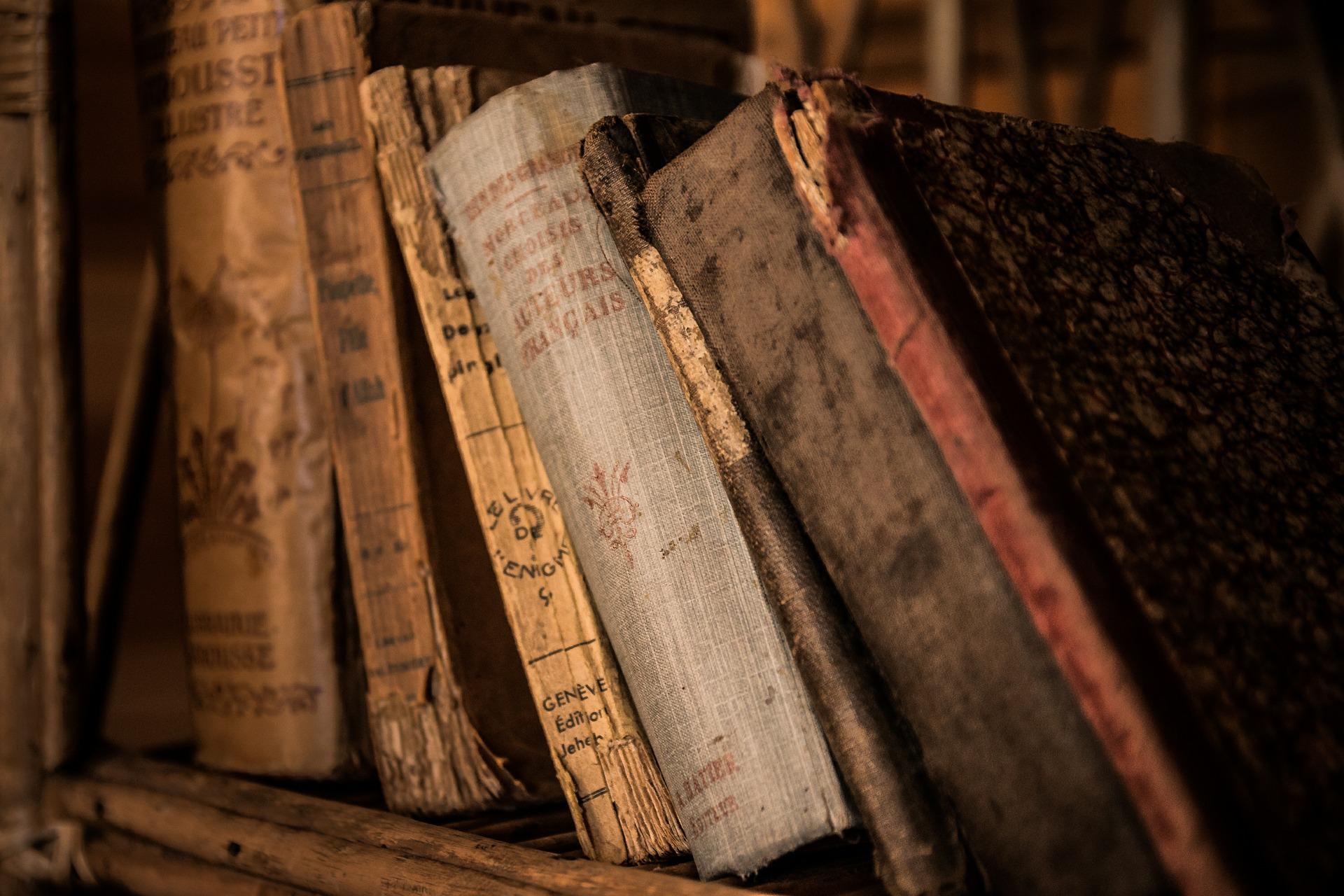
- 世界初の原産地呼称は1756年ポルトガル(所説あり)
- 超基本の1935年フランスA.O.C.法制定
- 制定された国の順序も把握しておくと覚えやすい
何といってもまずはフランスのA.O.C.法が制定された1935年を覚えましょう。
ワインを勉強している人であれば、”1935年”という年号を見ただけで「A.O.C.法制定の年だな」と頭に浮かぶほどの常識です。
そして次に世界初の原産地呼称法であるポルトガルの1756年。
「世界初」という部分は所説あるようですが、ソムリエ教本では「世界初は1756年のポルトガル」となっているのでこれで覚えておきましょう。
それ以外は若干優先度が落ちるものの、ニューワールドの各年号は出題されやすいので頭に入れておきたいところ。
ここでは「主要各国のワイン法制定年」を年表にしました。
国によっては「ワイン法の制定年」と「原産地呼称の制定年」が違うことがあるので注意してください。
| 年 | 備考 |
| 1756年 | ポルトガル原産地呼称ワイン法制定(世界初) |
| 1932年 | スペインワイン法D.O.制定 |
| 1935年 | フランスワイン法A.O.C.制定 |
| 1959年 | アルゼンチンワイン法「法律14878」公布 |
| 1963年 | イタリアワイン法D.O.C.制定 |
| 1973年 | 南アフリカワイン法W.O.制定 |
| 1978年 | アメリカワイン法A.V.A.制定(TTB管理) |
| 1986年 | チリのワイン法「法律18455・農業省令No.78」制定 ※原産地呼称D.O.は1994年制定 |
| 1993年 | オーストラリアワイン法G.I.導入 |
| 1994年 | チリの原産地呼称D.O.制定 |
| 2007年 | ニュージーランドのラベル表記に85%ルール適用 |
| 2017年 | ニュージーランドでG.I.制度成立 |
日本のワイン産業の歴史

- 甲州の由来となる2つの説
- 山田宥教と詫間憲久のワイン造り
- 各G.I.認定年
- 各O.I.V.登録年
ソムリエ&ワインエキスパート試験は日本ソムリエ協会が主催する呼称試験です。
自国である日本の歴史については他の国よりも詳しく学んでほしいようで、出題頻度にもそれが顕著に出ています。
特に、甲州の由来となる「718年大善寺説」「1186年雨宮勘解由説」、山田宥教・詫間憲久がワイン造りを始めた1874年、大日本山梨葡萄酒会社(のちにメルシャンになる会社)が設立された1877年、のように何かの起源に関する年号は1ケタ代までしっかり覚えてください。
「各G.I.の認定年」「O.I.V.の登録年」は基本中の基本です。
問われたら即答というくらいに仕上げておきましょう。
細かい部分では、長野や山梨独自の産地呼称制度の年や、各団体の設立年なども出題された実績があります。
山幸のO.I.V.登録や山形・長野・大阪のG.I.認定はごく最近の出来事です。
出題の可能性が特に高いので要注意!
この関係性も紐づけておきましょう。
| 年 | 備考 |
| 718年 | 甲州の由来の一つである大善寺説(行基) |
| 1186年 | 甲州の由来の一つである雨宮勘解由説 |
| 1874年 | 山田宥教・詫間憲久が甲府でワイン造りを始める |
| 1877年 | 大日本山梨葡萄酒会社設立 |
| 2002年 | 長野県原産地呼称管理制度創設 |
| 2008年 | 山梨県北杜市が日本初のワイン特区に認定 |
| 2009年 | Koshu of Japan設立 |
| 2010年 | 甲州がO.I.V.に登録 甲州市原産地呼称ワイン認定制度設立 |
| 2013年 | 山梨県がG.I.に指定 マスカットベーリーAがO.I.V.に登録 長野県信州ワインバレー構想 |
| 2018年 | 北海道がG.I.に指定 日本で「ワインのラベル表示ルール」施行 |
| 2020年 | 山幸がO.I.V.に登録 |
| 2021年 | 山形県・長野県・大阪府がG.I.に指定 長野県原産地呼称管理制度⇒長野プレミアムに移行 |
その他の重要事項

- フランスメドック地方の格付け
- アメリカの禁酒法
- 最初に〇〇した年
アメリカの禁酒法の期間や、最初にワインが造られた等の「最初に○○した年」はよく出題されます。
それぞれ国のワイン産業に大きく影響を与えた年となるので、出来るだけ覚えていきましょう。
また、ボルドーワインのブランドを確立した1855年メドック地方の格付けは、年号を見ただけで「メドック格付け」が思い浮かぶくらいにしておきたいです。
これまでの項目に比べると暗記の項目数は少ないですが、「誰が何をした」というところまで覚えたいので暗記のカロリーは変わらず高め。
| 年 | 備考 |
| 1659年 | 2月2日南アフリカで最初のワインが造られる |
| 1788年 | オーストラリアに最初のブドウ樹が植えられる(アーサーフィリップ) |
| 1825年 | オーストラリアハンターヴァレーに本格的なブドウ園が開設(ジェームズバズビー) |
| 1836年 | ニュージーランドで最初のワインが造られる(ジェームズバズビー) |
| 1852年 | シルベストレオチャガビアがチリにブドウ樹を持ち込む |
| 1855年 | フランスメドック地方の格付け |
| 1920年 | アメリカ禁酒法(1933年までの13年間) |
| 1976年 | パリ・テイスティング(パリスの審判) |
まとめ年表
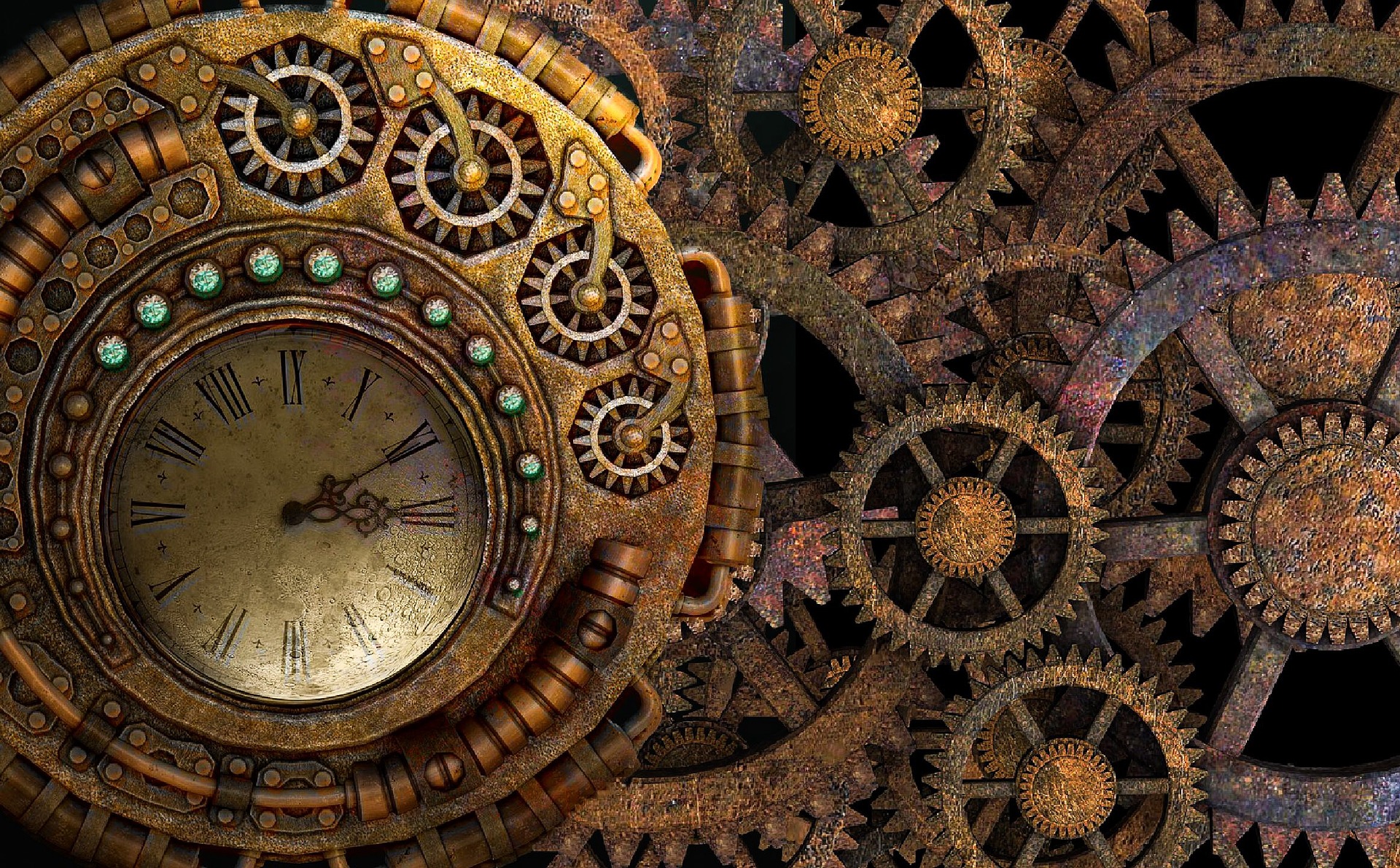
これまで解説してきた3項目を1つにまとめた年表も載せておきます。
それぞれ時系列の確認や、学習の仕上げに使ってください。
| 年 | 備考 |
| 718年 | 甲州の由来の一つである大善寺説(行基) |
| 1186年 | 甲州の由来の一つである雨宮勘解由説 |
| 1659年 | 2月2日南アフリカで最初のワインが造られる |
| 1756年 | ポルトガル原産地呼称ワイン法制定(世界初) |
| 1788年 | オーストラリアに最初のブドウ樹が植えられる(アーサーフィリップ) |
| 1825年 | オーストラリアハンターヴァレーに本格的なブドウ園が開設(ジェームズバズビー) |
| 1836年 | ニュージーランドで最初のワインが造られる(ジェームズバズビー) |
| 1852年 | シルベストレオチャガビアがチリにブドウ樹を持ち込む |
| 1855年 | フランスメドック地方の格付け |
| 1874年 | 山田宥教・詫間憲久が甲府でワイン造りを始める |
| 1877年 | 大日本山梨葡萄酒会社設立 |
| 1920年 | アメリカ禁酒法(1933年までの13年間) |
| 1932年 | スペインワイン法D.O.制定 |
| 1935年 | フランスワイン法A.O.C.制定 |
| 1959年 | アルゼンチンワイン法「法律14878」公布 |
| 1963年 | イタリアワイン法D.O.C.制定 |
| 1973年 | 南アフリカワイン法W.O.制定 |
| 1976年 | パリ・テイスティング(パリスの審判) |
| 1978年 | アメリカワイン法A.V.A.制定(TTB管理) |
| 1986年 | チリのワイン法「法律18455・農業省令No.78」制定 ※原産地呼称D.O.は1994年制定 |
| 1993年 | オーストラリアワイン法G.I.導入 |
| 1994年 | チリの原産地呼称D.O.制定 |
| 2002年 | 長野県原産地呼称管理制度創設 |
| 2007年 | ニュージーランドのラベル表記に85%ルール適用 |
| 2008年 | 山梨県北杜市が日本初のワイン特区に認定 |
| 2009年 | Koshu of Japan設立 |
| 2010年 | 甲州がO.I.V.に登録 甲州市原産地呼称ワイン認定制度設立 |
| 2013年 | 山梨県がG.I.に指定 マスカットベーリーAがO.I.V.に登録 長野県信州ワインバレー構想 |
| 2017年 | ニュージーランドでG.I.制度成立 |
| 2018年 | 北海道がG.I.に指定 日本で「ワインのラベル表示ルール」施行 |
| 2020年 | 山幸がO.I.V.に登録 |
| 2021年 | 山形県・長野県・大阪府がG.I.に指定 長野県原産地呼称管理制度⇒長野プレミアムに移行 |
年号練習問題

本記事で解説した主要ワイン史の年号について、ランダムで出題される練習問題を作成しました。
暗記の仕上げにご活用ください。
最後に
- ワイン法制定や最初に〇〇した年など出題しやすいポイントを把握する
- 世界初の原産地呼称は1756年ポルトガル(所説あり)
- 超基本の1935年フランスA.O.C.法制定
- 制定された国の順序も把握しておくと覚えやすい
- 日本の歴史については問題にされることが多い
- 甲州の由来となる2つの説
- 山田宥教と詫間憲久のワイン造り
- 各G.I.認定年と各O.I.V.登録年
- フランスメドック地方の格付け
- アメリカの禁酒法
- 最初に○〇した年
ワインがもつ長い歴史を知ると、ワインをさらに味わい深くすることができます。
試験のために細かい年号の数字を覚えるだけに留まらず、それぞれの歴史を深く調べてみるのも楽しいかもしれませんね。
ソムリエワインエキスパート試験の勉強法はこちら↓
ソムリエ・ワインエキスパート試験はワインの難関試験です。 勉強も大変そうだし、何から手をつけたらいいのかもわからないですよね。 筆者は年末頃から少しずつ勉強をスタートして、年明けからはオンラインスクールも利用しながら一発で合格す[…]
試験に向けてワインスクールを探している人はこちら↓
今回はソムリエワインエキスパート試験対策講座をオンラインで受講できるオススメなワインスクールTOP3をランキング形式で紹介します。 「仕事や家事が忙しくて定期的にスクールに通えない」 「通学圏内にワインスクールがない」 こんな人には自[…]